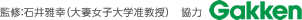木の実験・観察
研究室
木はどんな性質(せいしつ)をもっているのかな?
かんたんにできる観察から、楽しい実験まで、
きみの興味(きょうみ)に合わせてやってみよう!

葉には、すじがある。これを葉脈というんだ。葉脈は、くきから水を運ぶための通り道だ。また、葉でできた養分を、くきへ運ぶ道でもあるよ。
葉脈だけを取り出してみよう。きれいな「しおり」になるよ。
ナンテンやヒイラギの葉がやりやすいよ。
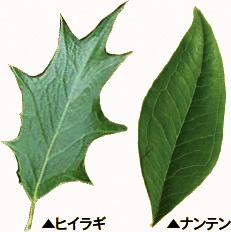

- 実験は、必ずおうちの人といっしょにしよう。
- 実験前にこの実験方法をしっかり読んで、まちがった手順で行わないようにしよう。
- 実験に使う材料は、おうちの人に用意してもらうこと。
- 材料をなめたり、口に入れたりしないこと。
- 材料がついた手で目をこすったりしないように気をつけよう。
- 火を使うときは、おうちの人にやってもらおう。
- 火をつけるときは、まわりに燃えやすいものがないのを確かめ、絶対にそばをはなれないこと。
- 実験のあとは、おうちの人といっしょに手や道具をきれいにあらい、しっかりあとかたづけをしよう。
用意するもの

重曹ってなに?
正式には、炭酸水素(たんさんすいそ)ナトリウムという。水にとけたものはアルカリ性(せい)。アルカリ性のものは、タンパク質(しつ)をとかす。熱を加えると、二酸化炭素(にさんかたんそ)のあわを出し、水と炭酸ナトリウムに変わる。炭酸ナトリウムもアルカリ性。
実験しよう!
-
 1
1水400mLを、なべに入れる。 ※アルミのなべは使わないこと。
-
 2
2ふっとうしたら、弱火にし、
重曹を大さじ3ばい入れる。 -
 3
3よくかきまぜる。
あわがたくさん出る。 -
 4
4葉を入れる。
弱火で30分ゆでる。 -
 5
5葉はうくので、ときどきはしでうら返す。湯気が手にあたると熱いので、はしは長めのほうがいい。
-
 6
6湯が茶色くなる。
30分したら、火を止める。 -
 7
7葉を取り出し、水に入れる。
冷やしながらよくすすぐ。 -

手でこするときは、必ずポリエチレンの手ぶくろなどをしよう
8ポリエチレンなどのてぶくろをして、つめでこすると、葉脈以外のところがとれる。
-
 9
9使わなくなった歯ブラシで軽くこすってもよい。とりにくいときは、さらに少しゆでてみよう。
-
 10
10葉を水であらい、
かわいたらできあがり。
緑色の葉のときはわからなかった、細かい葉脈が見える。水や養分の通り道は、葉にくまなくはりめぐらされていることがわかる。