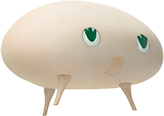
森の樹木図鑑
樹木についての知識がたっぷり。
身近な木や、住まいの地域にぴったりの木を探せます。
シナ (榀)
シナノキ科
シナノキの樹皮繊維はきわめて強く、古くはこの繊維から布や縄、畳糸(タタミイト)などがつくられていました。シナの語源は「結ぶ、くばる、くくる」という意味のアイヌ語だといわれますが、それはこうした用途からきているものでしょう。
一方、木材としてのシナノキはとても軽軟で、扱いやすいけれど個性に乏しい木。加工性のよさや材面の控えめな表情を活かし、合板の材料にすることが一番の用途です。また、シナノキはほぼ日本全国に育つため、数多くの方言名が生まれています。
シナ・シナカワの他、東北地方ではマダ・モウダ、西日本ではヘラ、中国地方ではアサジ・ヒルカワ・ネン、四国ではタク・フユギなどと呼ばれます。
よく似た種のオオバボダイジュをアオシナと俗称するのに対して、アカシナと呼ぶこともあります。
【材質】
散孔材で心材と辺材の差はやや不明瞭。心材は淡黄褐色、辺材は淡黄白色。肌目は精、木目はほぼまっすぐ。年輪はやや不明瞭。材が全体に軽軟均質で加工しやすい。保存性が低く、水湿に弱い。耐朽性が低い。仕上げのよさは中庸。
【生育地】
北海道、本州、四国、九州。特に北海道産が有名。
【住まいでの用途】
シナ合板の名前の通り、合板が第一の用途。押入れの内貼りによく使われる。
最近は特にランバーコア合板として利用されている。
ただし材が接着剤を吸収しすぎるのでユリア樹脂接着剤を使うと接着不良となることがある。
他にはベニヤ、パーティクルボード、ファイバーボード用材など。
- 関連する木:
- シナノキ


